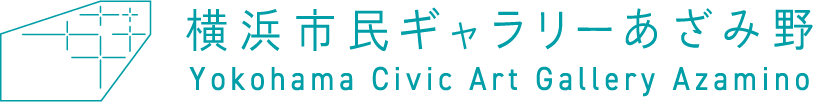メガレトスコープ[横浜市所蔵カメラ・写真コレクション]
カルロ・ポンティ/1860年
メガレトスコープ(Megalethoscope)は、イタリア・ベネチアの写真家でレンズメーカーでもあったカルロ・ポンティ(1822年頃~1893年)が考案した、写真を観賞するためのユニークな装置である。
ポンティは1860年代初頭、最初「アレトスコープ」(Alethoscope)と名づけたレンズ付装置を作成し、数年後、機能と装飾部分などをバージョン・アップさせた「メガレトスコープ」を発表する。
ポンティは1860年代初頭、最初「アレトスコープ」(Alethoscope)と名づけたレンズ付装置を作成し、数年後、機能と装飾部分などをバージョン・アップさせた「メガレトスコープ」を発表する。
装置
一見家具のようだが、立派な光学装置である。前側直方体にはレンズが仕込まれ、側面レバーで焦点調節もでき、見やすいよう外光を遮るフードも付けられている。装置の後半は後ろ側に開いた形の台形で、光を取り入れ鑑賞する写真を入れ込むようになっている。コレクションのバージョンには、この台形の四面と背面に豪華な彫刻が施され、「写真」を象徴すると思われる膝元にカメラを置きネガを見る女性像をはじめ、それぞれ異なるシンボルが彫られている。光を採りこむのには反射光、透過光のどちらかを選べる。
台形の上面と側面(装置が回転し、縦長と横長両方の写真に対応)の扉が開くと、写真の表面に光が反射しレンズを通して拡大された風景が目の前に広がる。それを閉じて背後から太陽光またはランプの光を取り込むと、写真の印象は大きく変わる。同じ写真が夜景に早変りするのだ。
台形の上面と側面(装置が回転し、縦長と横長両方の写真に対応)の扉が開くと、写真の表面に光が反射しレンズを通して拡大された風景が目の前に広がる。それを閉じて背後から太陽光またはランプの光を取り込むと、写真の印象は大きく変わる。同じ写真が夜景に早変りするのだ。

カルロ・ポンティ
1860年代
Megalethoscope/Carlo Ponti/1860s
写真スライド
その仕掛けは写真に秘密がある。木枠に張られた写真の背後には、彩色された裏紙がついており、背後から光を当てると色が透過し華やかでファンタジックな夜の光景を演出する。
写真の表面には大小細かな針穴が開いていて、光がもれて街灯や様々な祝祭的なイルミネーション、はたまた火山の噴火口や静かな水辺の光の反射なども表現する。
夜景バージョンの表現には強い印象を与えるものもあり、写真に色彩が加味されているだけとは言い難く、夜景の光と闇の対比が作り出す独特の奥行きや、きらびやかな色彩を際立たせ、元の写真とは全く異なる情景を浮び上がらせる。
写真の表面には大小細かな針穴が開いていて、光がもれて街灯や様々な祝祭的なイルミネーション、はたまた火山の噴火口や静かな水辺の光の反射なども表現する。
夜景バージョンの表現には強い印象を与えるものもあり、写真に色彩が加味されているだけとは言い難く、夜景の光と闇の対比が作り出す独特の奥行きや、きらびやかな色彩を際立たせ、元の写真とは全く異なる情景を浮び上がらせる。


メガレトスコープのルーツ
写真の記録性を利用しながら同時にファンタジーも求める映像世界は、20世紀に大きく華花開いた映画にも受け継がれた、矛盾しつつも実は伝統的なあり方だ。
一枚の画像で昼と夜の情景を楽しむこの装置のアイディアには、直接の影響を与えた先祖がある。かつてパリやロンドンの繁華街で大人気だった娯楽施設「ディオラマ館」だ。それは奇しくも最初の実用的な写真術「ダゲレオタイプ」を発明したフランスのダゲールが、写真に携わる前の1822年頃に仲間と共同開発した娯楽施設だった。ダゲールは画家修業ののち舞台装置家として活躍し、光を操った斬新な舞台で大きな名声を得ていた。その延長線上で生まれたディオラマ館は、光そのものが中心となる見世物で、非常に迫真的に描かれた風景を、光の当て方を巧みに変えることによって、あたかも朝から夜までの一日の光の変化を体験できるという驚くべきものだった。その題材はスイスの渓谷など壮大な自然景観や、ゴシック様式の教会廃墟など想像力をかきたてる幻想的なもので、見る者を圧倒したと言われる。
一枚の画像で昼と夜の情景を楽しむこの装置のアイディアには、直接の影響を与えた先祖がある。かつてパリやロンドンの繁華街で大人気だった娯楽施設「ディオラマ館」だ。それは奇しくも最初の実用的な写真術「ダゲレオタイプ」を発明したフランスのダゲールが、写真に携わる前の1822年頃に仲間と共同開発した娯楽施設だった。ダゲールは画家修業ののち舞台装置家として活躍し、光を操った斬新な舞台で大きな名声を得ていた。その延長線上で生まれたディオラマ館は、光そのものが中心となる見世物で、非常に迫真的に描かれた風景を、光の当て方を巧みに変えることによって、あたかも朝から夜までの一日の光の変化を体験できるという驚くべきものだった。その題材はスイスの渓谷など壮大な自然景観や、ゴシック様式の教会廃墟など想像力をかきたてる幻想的なもので、見る者を圧倒したと言われる。
ポンティの写真
1850年代に開発された湿板写真は、画像の美しさに加え焼き増しもできたことから、社会の写真の需要を大きく増大させ、肖像だけでなく風景も新たな被写体になることを後押しした。
とりわけイタリアは、19世紀ヨーロッパ社会で高かった歴史的関心やロマンチックな憧憬の対象で早くから多くの写真家の被写体になったが、やがて交通が発達し人気の観光地になると、大量の写真がプリントされ販売された。ポンティはベネチアにある宮殿や教会建築の内部や外観、運河や街角など美しい写真を残したが、地元にはカルロ・ナヤなど他の優れた写真家もおり、ポンティは彼らの写真も入れた『ベネチアの記憶』という一連の写真アルバムを出版して、同地のイメージ発信役を演じたのである。メガレトスコープ用にはベネチア以外にもローマの古代遺跡フォロ・ロマーノやナポリ近郊のベスビオス火山をはじめ、イタリアを中心とした様々な風景写真が用いられている。
阿部 聡子(写真史研究家)
とりわけイタリアは、19世紀ヨーロッパ社会で高かった歴史的関心やロマンチックな憧憬の対象で早くから多くの写真家の被写体になったが、やがて交通が発達し人気の観光地になると、大量の写真がプリントされ販売された。ポンティはベネチアにある宮殿や教会建築の内部や外観、運河や街角など美しい写真を残したが、地元にはカルロ・ナヤなど他の優れた写真家もおり、ポンティは彼らの写真も入れた『ベネチアの記憶』という一連の写真アルバムを出版して、同地のイメージ発信役を演じたのである。メガレトスコープ用にはベネチア以外にもローマの古代遺跡フォロ・ロマーノやナポリ近郊のベスビオス火山をはじめ、イタリアを中心とした様々な風景写真が用いられている。
阿部 聡子(写真史研究家)